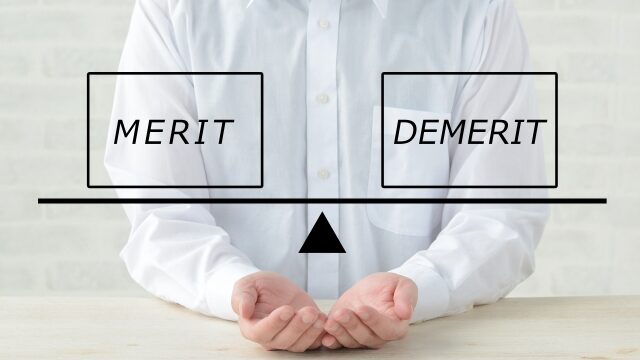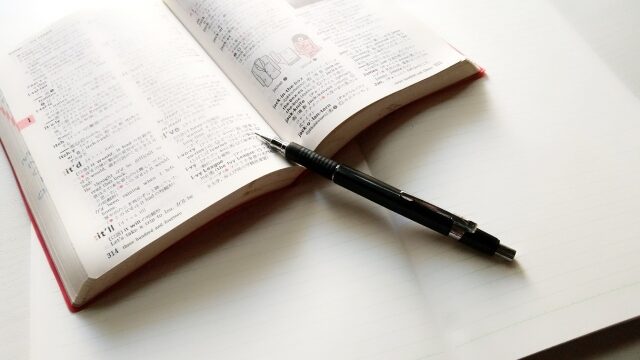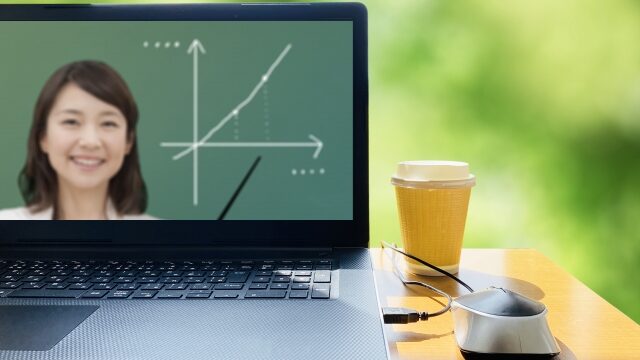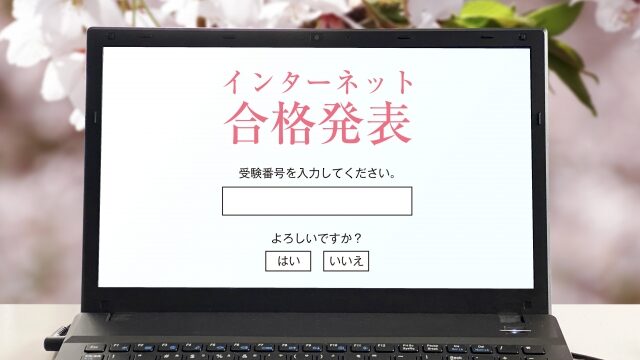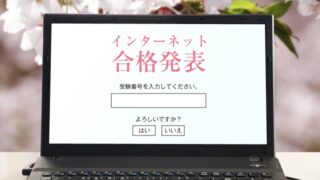公立中高一貫校に向いている子とは 合格する子はどんな子?

公立中高一貫校に向いている子ってどんな子なんだろう?
お母さんたちの間でなかなか答えが出ないこの疑問。
公立中高一貫校は適性検査、作文、内申で合否が決まると言われていますが、実際、この子は受かる!と言われた子が落ちていたり、どうですかねぇ・・・と言われた子が合格していたり。
いろんなケースがありすぎて、公立中高一貫校はこうすれば合格するよ!公立中高一貫校に向いている子はこういう子だよ!という基準が無くて、不安になりがちですよね。
この記事では公立中高一貫校に向いている子について書いていこうと思います。
公立中高一貫校に向いている子という明確なものはない
ちょっと昔までは公立中高一貫校に向いている子は「積極性のある子」と言われたこともありました。
それは第1期生が積極的過ぎて係がなかなか決まらないと言った話があったからのようです。
でも普通に考えて、中学受験をしようと考えて勉強を頑張ってきた子というのは、小学校の中でもお勉強のよくできる良い子ちゃんが多かったはず。
先生からも褒められ、頼られ、いろんな係を任されてきた子が多いはずなんです。
その子たちが1か所に集まったら、そりゃあ、みんなより自分がと思って手を上げる子ばかりになるのは当たり前だと思いませんか?
私立中高一貫校でもこういったことはよく起こっているし、現に、私立中高一貫校の中1の最初のクラス委員に立候補する子はクラスの約半数を超えることもあるんです。
県立高校の進学校だって、一番最初のクラス委員は立候補ですぐに決まりますしね。
だから公立中高一貫校には積極的な子が向いているなんて言う情報はまあ、あやしいもんですよね。
これまで先生に褒められてきた子が多いからこそ、積極性も身に付いているし自信もあるんです。
そう考えると逆に、公立中高一貫校に向いている子というよりは、公立中高一貫校を目指す子というのは、
- 小さいころからお勉強を頑張っている子
- 家庭でのしつけができている子(小学生らしい常識のある子)
- いわゆる良い子
- 学校の先生を困らせない子
が多いのかなと思います。
つまりは宿題を忘れたり、お友達に意地悪して泣かせて先生に怒られたみたいな子は少ないんだろうなという想像ができますよね。
中学受験の勉強というのはだいたい、小4か小5くらいから親が意識して始めさせる家が多いので、小4か小5くらいから学校生活でもちゃんとするんだよとかそういった声掛けも家庭で増えていているはず。
そうなると、子供は学校でも良い子にするし、塾でも勉強しているから宿題なんて悩まずにすぐに終わるし、学校の授業でも物わかりの良い手のかからない子になるし。
まあ、そういうことなんだろうなと思います。
結局は、がんばって勉強して合格のために気を使っている子が多いんだと思います。
それは私立中高一貫校でも同じなんですけど、私立中高一貫校は頭の体操が必要な問題が多いのもあって、ちょっとへんくつな変わった男子とか向いていると言われることもあるんですけどまあ、ある意味偏見ですよね。
スポンサーリンク公立中高一貫校に向いている子で合格できる子はこんな子
公立中高一貫校に向いている子、合格できる子というのはずばり
当日のテストで点数が取れて作文がしっかり書けた子
です。
そんなの当たり前じゃないか!って思いましたか?
でも、公立中高一貫校の適性テストっていくら対策してもその時そのテストで自分の得意分野が出たら書きやすいけど、そうじゃないと書きにくかったり、その書き方が受験する学校の先生にあまり良い評価をされなかったら点数が低くなったりしますよね。
塾の先生や通信教育の先生に指導してもらうと分かるんですけど、先生によって添削がちょっとずつ違うんです。
短答問題のように、これは「ア」これは「③」とか答えが決まっていれば添削に差は出ないんですけど、記述問題を添削するってやっぱり個人の裁量が結構出てきます。
理科とか社会の記述問題みたいに、これとこれの言葉が入っていれば○とか、国語の記述問題みたいに、お父さんが悪いということとこれから気をつけようという気持ちが書かれていれば○とか、そういう決まりがあればいいんですけどね。
基準を決めた先生によって点数が上下するところが結構あるんじゃないかなと、問題を見ていて思うんです。
そういうところで言うと、
その学校の先生と相性がいい子
が合格しているのかな?とも思えます。
結局、どんな子が合格するのか、どんな子が公立中高一貫校に向いている子なのかというのは私達には分からないのですが
きっと、丸付けの現場にいってその解答を見比べてみた時、「あぁ、、、なるほどね・・・」と納得出来たりはするんだろうなと思う次第です。
どんな子が向いているのだろう?ではなく、もし公立中高一貫校を目指そう、目指したいと決めたなら、受検に向けてできることを精一杯やって準備しましょう。
また何が基準か分からないので、いろんな経験をしていろんな話や考え方の引き出しを作ってあげておきましょう。
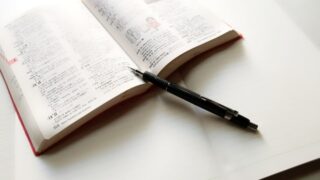


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/44353b58.35afe684.44353b59.0fb60081/?me_id=1404278&item_id=10002018&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fluluhope%2Fcabinet%2Fhom%2Fhom_001%2Fhom-0016_00.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)